「最近、娘が急に『パパ嫌い!』と言い出してショック…」とお悩みの方へ。
本記事では、子どもが突如お父さんを拒否する“父イヤイヤ期”をどう乗り越えるか、実際の体験を交えながら対処法をまとめました。
我が家では長女“みっこ”が妹(または弟)の誕生を控えており、さらにお姉ちゃんらしく成長を目指す中で、定期的に訪れる“パパ拒否”をどう受け止めるかが大きなテーマ。
自分に原因があると分かっていても、やっぱり凹む…そんなお父さん必見のヒント満載です。
1.ブログを始めたきっかけと我が家の背景
はじめまして、当ブログ「みっこのねえねブログ」を運営している父(通称:とと)です。
我が家には6歳の娘「みっこ」がいて、さらに夏には新しい家族が増える予定。妻(かか)は現在妊娠中で、みっこは「やっと私もお姉ちゃんになれる!」と大はしゃぎの日々を送っています。
しかし、この「待望のきょうだいができる!」というハッピーな話に隠れるように、定期的に訪れるちょっとした問題が…。そう、それが今回のテーマである“父イヤイヤ期”です。
娘が小さいころから、いわゆる“イヤイヤ期”は何度か経験してきましたが、最近では「お父さんなんて嫌い!」「パパとなんか話したくない!」と直接的に拒否されることも増えてきました。原因としては思い当たる節がありすぎるので、悲しいけれど納得もしているのが正直なところ…。
本当は「パパはあなたのことが大好きだよ!」とアピールしたいのですが、毎朝の余裕のなさや、仕事の忙しさからついイライラをぶつけてしまったり。これじゃあ「嫌い」って言われても仕方ないのかな、と。
とはいえ、やっぱり「嫌い!」と言われると凹みますよね。これを乗り越えて、娘にとって自慢の「お父さん」でいられるようになるにはどうすればいいのか――。同じように悩むパパさんの参考になればと思い、今回は我が家の具体的なエピソードや対処法をまとめてみました。
2.“父イヤイヤ期”って何? みっこ流「お父さん嫌い」の実態
「お父さん嫌い期」「父イヤイヤ期」と呼ばれる時期は、一般的に幼児~小学校低学年くらいで訪れることがあります。
我が家では、みっこの「お父さん嫌い!」発言が急増するタイミングが、だいたい
- 朝にパパがイライラしながら支度をしているとき
- 夜遅くに疲れて帰ってきて、すぐにイライラをぶつけてしまったとき
- 週末に“お父さん”の都合で外出の予定を変更してしまったとき
の3パターンに集中しています。
具体的には、朝起こすときに「早くしなさい!」と強い口調になったり、保育園や習い事の送迎で時間がないからとつい怒鳴ってしまったり…。また、せっかくのお休みなのにパパ側の事情(仕事の用事や趣味など)で遊びに行けなくなったりすると、みっこの機嫌は一気に下降。
そんな些細なことで「もうパパ嫌い!」の宣言が出るわけです。機嫌がいいときはそんなこと言わないんですけどね…。“子どもは気分屋”と言うけど、本当にそうなんだなと実感しています。
3.なぜ嫌われちゃうの? よくある原因とパパの反省点
子どもの「お父さん嫌い!」には、もちろん子どもなりの理由があります。代表的なものを挙げると
① 父が感情的になりがち
仕事で疲れていたり、時間に追われていたりすると、つい子どもにキツく当たってしまいがち。「パパ怖い…」「パパ怒ってばかり…」と思われると、当然嫌われても不思議はないですよね。
② 母との対比
我が家の場合、かかはいつもニコニコで優しいタイプ。みっこにとっては一番安心できる存在です。それに対して、お父さんは「あれやった? 早く!」「宿題やったの?」と指示や注意ばかり。となると、子どもは「ママの方がいいや…」となるのも自然な流れ。
③ 子どもとの接触時間が少ない
朝はバタバタ、夜は遅く帰ってきてすぐ寝る、といった具合で、実質的に子どもとゆっくり触れ合う時間が取れていないパパも多いですよね。コミュニケーション不足が原因で、子どもが「あんまりパパのこと知らない…」と感じてしまうケースも。
私自身も「朝から機嫌が悪い」「疲れて帰ってきたらすぐイライラ」など、思い当たる節が多々あります…。みっこが「あ、パパが怒りそうだな」と察知しただけでテンションが下がり、「もうパパ嫌い!」になってしまうんでしょうね。自業自得と言われても仕方ないかもしれません。
4.父イヤイヤ期に試してみた対処法5選
では、具体的にどうやって父イヤイヤ期を乗り越えればいいのか。私がいろいろ試行錯誤してみた中で、効果があったと感じる方法を5つご紹介します。
① 朝にゆとりを持つ
バタバタしていると、つい「早くしなさい!」と怒鳴ってしまいがち。そこで、少し早起きして自分の身支度を先に済ませるようにしました。心にゆとりがあるだけで、娘にも優しく接することができ、ギスギスしにくくなります。
② スキンシップの時間を確保する
子どもは親とのスキンシップを通じて安心感や親密感を育んでいきます。1日5分でも10分でもいいので、抱っこしたり、一緒に絵本を読んだりする時間をつくることを意識しました。
③ 「ありがとう」を積極的に伝える
仕事が忙しいときほど、家族に対して「ありがとう」「助かったよ」といった感謝の言葉を忘れがち。娘が小さなことを手伝ってくれたときも、しっかり言葉にすることで「パパは私のことが大好きなんだ!」と感じてもらえるよう意識しています。
④ 子ども目線で話を聞く
大人はどうしても「早く」「ちゃんと」「きちんと」といった言葉ばかり使いがち。娘が何か話しかけてきたときはスマホを置いて、目線の高さを合わせて「うんうん、なるほどね」と共感を示すようにしたら、会話の質がぐっと変わりました。
⑤ 親のイライラ発散方法を見直す
どうしてもイライラしてしまうときは、意識的にリフレッシュする方法を取り入れています。散歩をしたり、家族に事情を話してお風呂でゆっくりリラックスしたり…。自分のストレスをコントロールできれば、娘に当たることも減るはずです。
もちろん、これらを実践したからといって一瞬で「パパ大好き!」に戻るわけではありません。でも、続けることで以前よりは嫌われる頻度が減り、みっこが自然と甘えてくる瞬間も増えたように感じています。
5.長女お姉ちゃん化計画と父の苦悩
さて、我が家にはもうひとつの大きなミッションがあります。それが「みっこを立派なお姉ちゃん(ねえね)に育てる」こと。
みっこ本人も、「妹(弟)ができるなら、私がお姉ちゃんとしてしっかりしなきゃ!」という気持ちが強いようで、いろいろ手伝いや準備を張り切ってくれています。たとえば赤ちゃん用の服を選んだり、ぬいぐるみでお世話の練習をしたりと、頼もしさも感じるほど。
しかし、その一方で「パパ嫌い!」が出るときは、本当に冷たい(笑)。かかにはニコニコで寄り添って、赤ちゃんのお世話の話も盛り上がるのに、私が話しかけると「ふーん…」で終わることもしばしば。正直、ちょっと嫉妬しちゃいますよね。
私自身、「自分の子どもがふたりになるなんて嬉しい!」とワクワクしている反面、みっことの関係がぎくしゃくすると「もうすぐ生まれる子にも嫌われたらどうしよう…」と不安になることも。
でも、最近は「こういう時期なんだ」と割り切れるようになりました。子どもは成長段階で、必ずしもいつもパパにベッタリとは限りません。特に女の子はママとの結びつきが強いケースが多いと言われますし、パパにはパパの役割があります。
それでも自分なりに努力して、「お父さんって意外と面白いじゃん」「役に立つじゃん」と思ってもらえるよう行動を重ねていくことで、そのうち「パパ大好き!」と復活してくれるかも――と、のんびり期待しています。
6.まとめ:一過性だからこそ、今の関係を大切に
子どもが「お父さん嫌い!」と口にする時期は、決して少なくありません。専門家の話でも、それは成長の一環であり、やがては収まっていくことが多いそうです。
しかし、ただ受け身で「そのうち治るだろう」と放置していると、子どもとの距離がどんどん離れてしまうことも。日々の中で少しずつコミュニケーションを見直したり、イライラを減らす工夫をしたり、「嫌われないようにビクビクする」というよりは「ちゃんと伝えたいことを伝え、感謝を忘れない」姿勢が大切かなと感じています。
そして何より、子どもは気まぐれですから今日「パパ嫌い」と言っていても、明日にはケロッと「パパ一緒に遊ぼう!」なんてことも。そんな可愛い一面を見たら、昨日の言葉なんて全然気にしないというか、「やっぱり子どもって面白いな~」と思えるようになります。
要は一過性のものだからこそ、今ある関係を大切に育てつつ、焦らずに子どもを見守る。これは私たち親自身の精神面も楽にしてくれる考え方だと感じました。
「みっこのねえねブログ」では、今後もみっこが妹(弟)の誕生に向けてどんな風に成長していくのか、そして私(とと)がどのように奮闘していくのかを、リアルに記録していきます。もし同じように「子どもに嫌われてツライ…」と感じている方がいたら、ぜひ一緒に乗り越えていきましょう!
7.おすすめ情報:パパのための子育てサポート活用法
最後に、父イヤイヤ期を乗り越えるためにも役立ちそうな子育てサポートをご紹介します。
① 父親向け交流会やコミュニティを探す
地域の子育て支援センターやSNSなどで、パパ同士が情報交換できるコミュニティが意外とあります。同じ悩みを持つパパ仲間と話をするだけでも「うちだけじゃないんだ」と安心できますし、具体的な対策のヒントを得られることも。
② 市区町村の子育てイベントに参加
自治体主催のイベントでは、親子で楽しめるプログラムも多く実施されています。特にパパが積極的に参加すると、子どもとの絆が深まるきっかけになるかも。
③ 子どもと楽しめる習い事やお出かけスポット
スポーツや音楽、アート系の習い事など、パパも一緒に体験できるものを選んでみるのもおすすめ。「パパと一緒だと楽しい!」という成功体験を積み重ねれば、父イヤイヤ期も少しずつやわらいでいく可能性があります。
④ 育児休業や有給休暇の活用
思い切って短期の育児休業や長期休暇を取れれば、子どもとの時間を増やす大チャンス。とはいえ職場の理解が必要なので難しい場合も多いですが、可能であれば検討してみる価値ありです。
ちょっとした工夫で親子関係は変わっていきます。「お父さんなんて嫌い!」の言葉ばかり気にしすぎず、長い目で見ながら、できることから試してみてくださいね。
以上、今回は定期的にやってくる「父イヤイヤ期」と、私(とと)が実践している対応策をご紹介しました。
日々イライラしたり、落ち込んだりしながらも、やっぱり子どもは可愛い存在。これからもみっこが妹(弟)の誕生に向けて、立派なお姉ちゃんになっていく様子を見守りつつ、父も成長していこうと思います。
次回のブログでは、春から始まったみっこの小学校生活の様子や、いよいよ近づいてくる出産に向けた準備などについて、のんびりと綴っていきますので、お楽しみに!
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
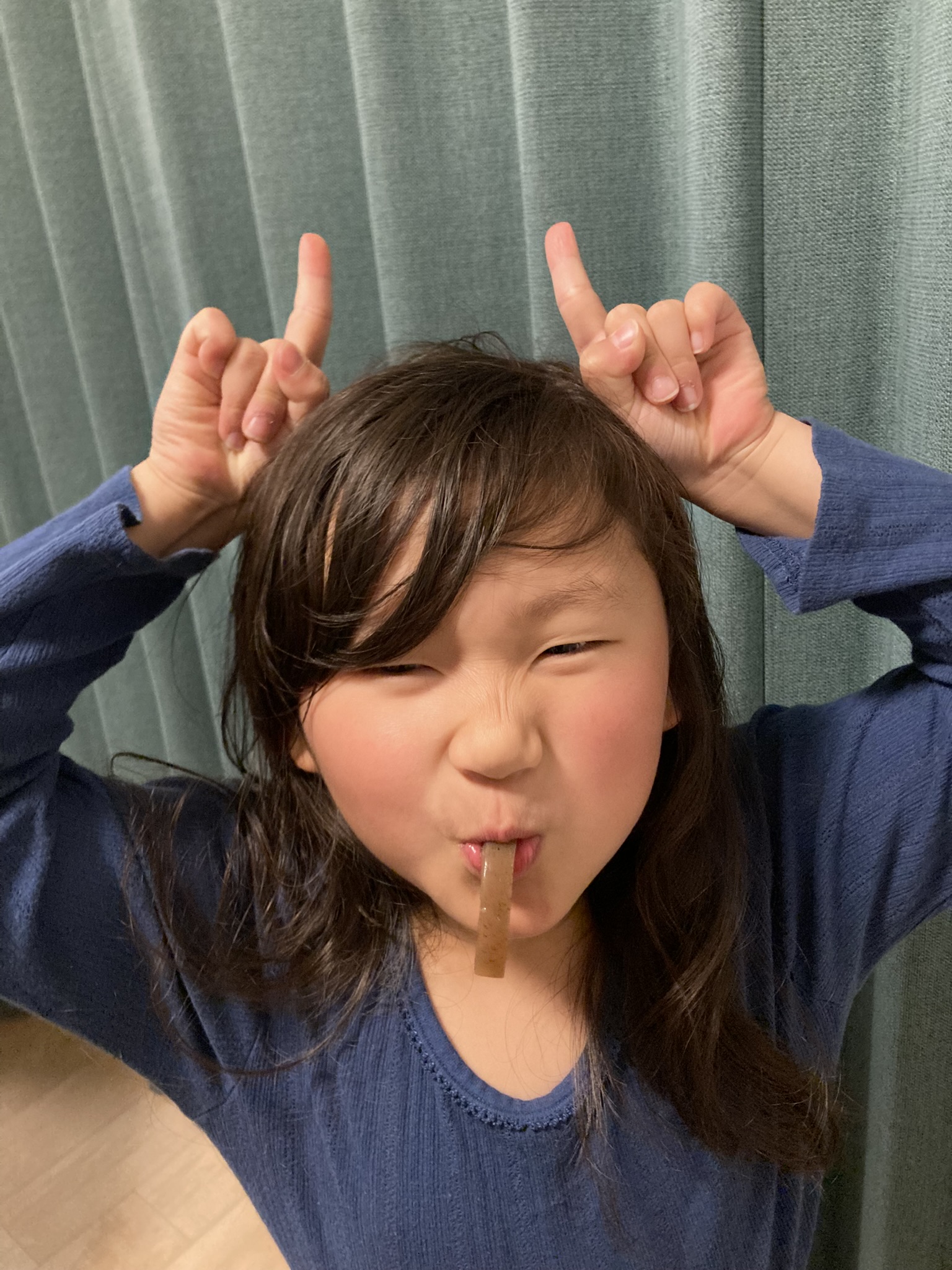


コメント